診療案内
外来担当医表Consultation hours
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 |
村岡 |
木下 |
村岡 |
村岡 |
小楠 |
村岡 |
| 14:00~16:00 |
梁井 |
木下 |
奥田 |
木下 |
小楠 |
|
| 16:00~19:00 |
村岡 |
村岡 |
村岡 |
村岡* |
村岡 |
※院長(村岡)の診察時間帯は患者様が多く、お待たせしてしまう場合があるため、できる限りお時間に余裕をもってご来院くださいますようお願いいたします。
※第三木曜日の18:00~19:00は、院長(村岡)不在のため、別の外来担当医に変更となります。
※公務により、18時以降の外来担当医が別の医師の担当となることがあります。
※毎月第2、第4土曜日は漢方の診療を受けることができます(三澤医師)。
※土曜日は助医による診察を行う場合があります。
※当院は複数の医師で診療を行っております(医師のご希望がある場合は事前にお電話でご確認ください。)
※循環器専門医の診療をご希望される場合は、院長(村岡)、木下、奥田の診療時間にご来院をお願いいたします。
※当院では女性医師による外来診療も行っております。女性医師の診察をご希望される場合は、木下、小楠の診察時間にご来院をお願いいたします。
※院長(村岡)の不在時は、小児科の診療を行っておりません。事前に診療時間をご確認ください。
※午前の受付終了時間は12:45まで、午後の受付終了時間は18:45までとなっております。 (患者様の来院状況によっては受付終了が早まる場合もあります)
※日曜日と祝日の外来は休診です(ご契約されている方の訪問診療や往診に関しては一部行っております。お気軽にご相談ください。)
医院概要・アクセスClinic Overview



| 医院名 | 薬院内科循環器クリニック |
|---|---|
| 主な診療科目 | 一般内科、循環器内科 |
| 住所 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 2階 |
| TEL | 092-738-0123 |
| 休診日 | 外来診療は日曜日・祝日が休診です。 (ご契約されている方の訪問診療や往診に関しては一部行っております。お気軽にご相談ください。) |
| 駐車場 | なし ※近隣のコインパーキングをご利用ください。 |
アクセスマップAccess Map


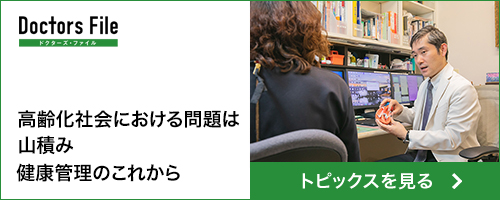
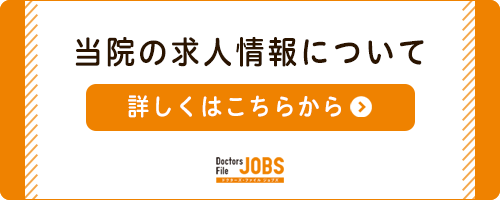


 TEL
TEL Web予約
Web予約